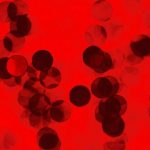ランナーそれぞれの身体に合ったフォームをつくるために知っておきたい4スタンス理論
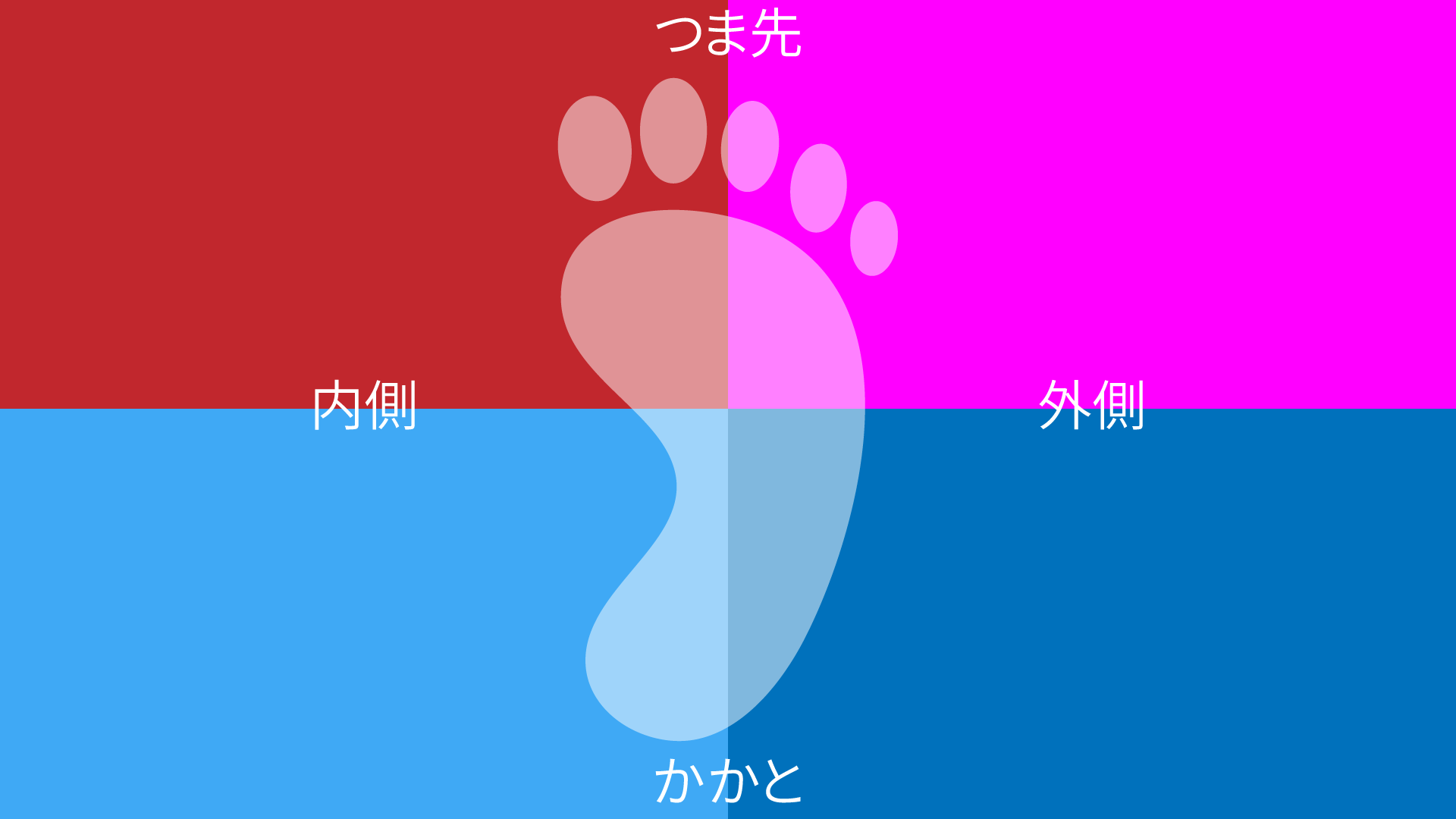
フォームの常識はランナーのよっては非常識
「腰高の意識で」「腕は後ろにできるだけ強く引く」「着地はかかとから」
上記のような言葉、よりよいランニングフォームを模索すべく、ランニングの専門書などを読んだことがある方なら一度は聞いたことがあるのでは?
これらのアドバイス、ランナーによっては大正解で、この通りに走ればパフォーマンスアップにつながる方は多くいらっしゃいます。
一方、これらのアドバイス通りにやっても一向にパフォーマンスアップしない、それどころか故障が増えてきた・・・などという方もおそらく相当数いらっしゃると思います。
身体の特徴はランナーそれぞれ
ランナーによって骨格も異なれば、筋肉のつき方も異なってと、身体の動かし方はそれぞれ。
そのためどの動きがランニングでは正解などというものは存在せず、身体の特徴を最大限に生かしたフォームは人によって大きく異なってきます。
そのため、今まで常識のように言われてきたランニングフォームの常識のようなものも、それがぴったり合う方もいれば、なぜか全くしっくり来ない方がいらっしゃるのも当然と言えば当然です。
ただそうは言うものの、「自分の身体に合ったフォームを身につけるための指針になるようなものが何か欲しい・・・」という方は多いのでは?
そんな方にオススメなのがここ最近何かと話題の「4スタンス理論」です。
4スタンス理論とは
4スタンス理論とは、人間には生まれついてきまった身体特性があり、その特性を共通する身体の使い方によって4つのタイプに分けて、そのタイプに合わせた身体の動かし方やトレーニング方法を考えていくというもの。
この4スタンス理論は2014年のお正月番組「さんタク」という番組で、明石家さんまさんと木村拓哉さんによって取り上げられた事をきっかけに、世に広く知られるようになりました。
この4スタンス理論はランニングだけでなく、ゴルフやテニスなど多くのスポーツでもこの理論が応用されていて、書店には多くの4スタンス理論関連の本が並んでいます。。
4スタンス理論はタイプ分けからスタート
4スタンス理論でタイプ分けをする際にポイントとなるのは、立っている時に無意識のうちにバランスを取ってくれている足裏。
この足裏の「つま先の内側」「つま先の外側」「かかとの内側」「かかとの外側」の4箇所のうち、どこを重心にした時にバランスが取りやすいかによって、4スタンス理論ではタイプ分けを行います。
ただし足裏の4箇所の中で、どこを重心にした時バランスを取りやすいかについては、ただ立っているだけではまず見分けがつきません。
そこでいろいろな姿勢をとったり、身体を動かしたりする数種類のテストによって、4つのどのタイプに当たるかを探っていくのが一般的です。
そのテストの方法については、また後日別の記事にさせていただくとして、今回の記事ではとりあえずこの「4スタンス理論」の名前だけしっかり覚えておいてください!

合同会社ランシスの運営を通じて「ランウォーク」×「ツーリズム」の掛け合わせ「ランウォークツーリズム」による、三重を走り歩く新たなモチベーション創りを模索しています。
またランニングコミュニティ「セカンドウィンド四日市」の運営や、三重県ウオーキング協会事務局長として広報等を担っています。